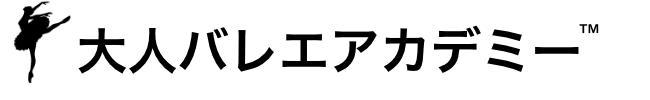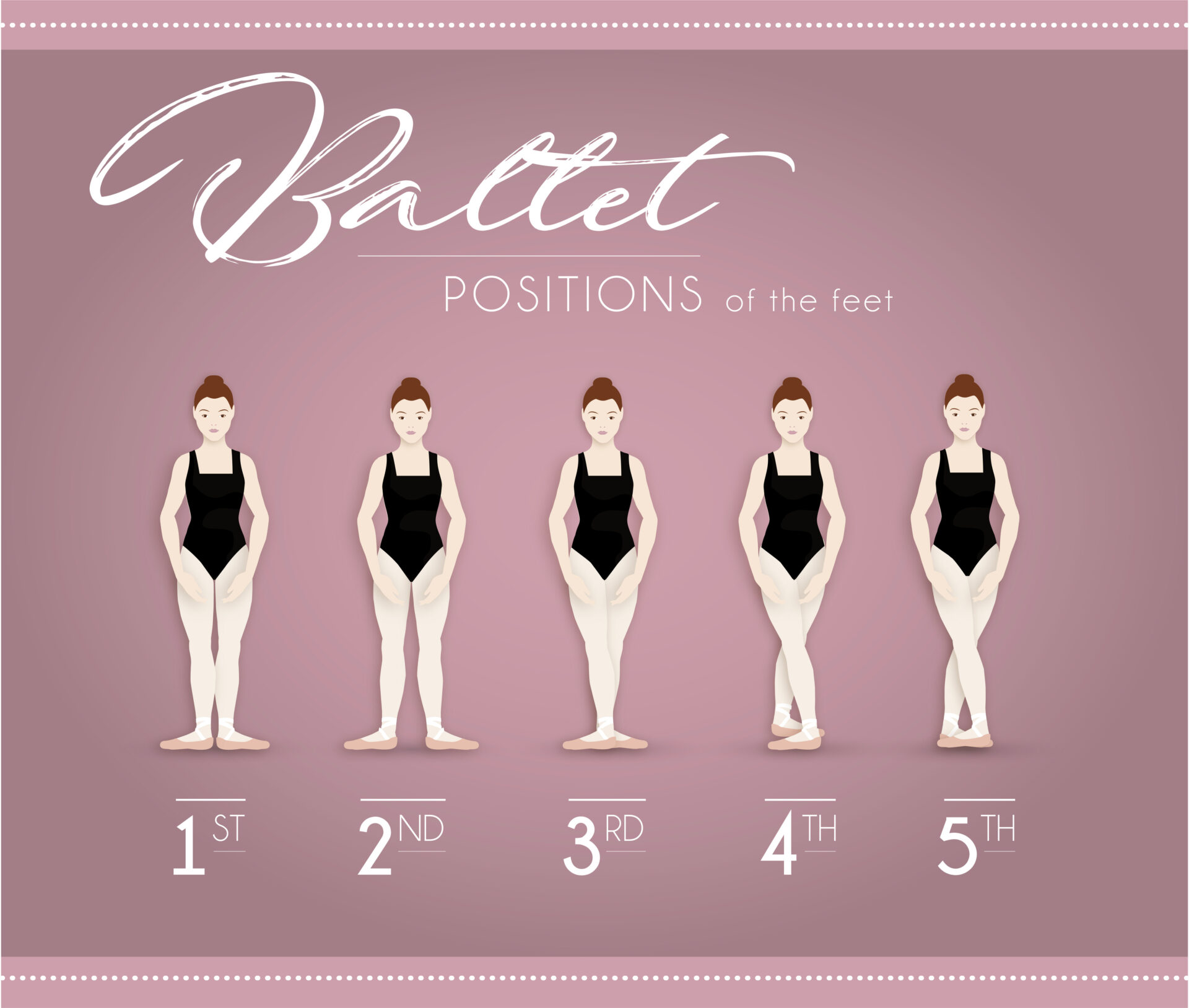こんにちは。大人バレエアカデミー™、バレエトレーニングディレクターの猪野です。
結論
当アカデミーでは、大人の初学者〜初級の基礎づくりに「3番ポジション」を標準採用しています。理解の乏しい方から5番ポジションを教えていない、という批判がありますが、目的は、安全に・崩れない基礎(アライメント/ターンアウト/引き上げ)を最短で定着させるため。上級ではもちろん5番も行いますが、順序を守るほうが上達が速く、ケガも少ないという方針です。
なぜ「いきなり5番」は非効率になりやすいのか
5番はクラシックの象徴的な形ですが、以下の理由で初期学習の妨げになりやすい面があります。
-
“見た目の交差”を優先しがち
股関節の外旋が未発達な段階で5番を形だけ作ると、足先のねじり・膝のねじれ・骨盤の前後傾で帳尻を合わせやすくなります。これはターンアウトの誤学習と膝・足首の負担増につながります。 -
大人の身体条件
可動域や既往歴、日常姿勢のクセにより、再現性の高い5番をいきなり作るのは難度が高め。再現性が低い練習は、**上達曲線を寝かせる(伸びにくくする)**要因になります。
3番ポジションが「最短で上達」につながる理由
1) 体軸と骨盤の中間位がつく
交差が浅い分、骨盤の向きと頭頸のバランスを保ちやすく、上半身の力みを減らせます。結果として、当校が定義する**「引き上げ」**(骨盤底筋と深層腹筋で内臓を上方固定→背骨に沿わせる)が入りやすくなります。
2) 股関節からのターンアウトが定着
足先のねじりで誤魔化せないため、深層外旋六筋の回旋と膝つま先の一致が習慣化。これが後々の**5番の“質”**を決定します。
3) 誤学習のリセットがしやすい
プリエ/タンデュ/デガジェの軌道や床とのコンタクトを丁寧に学べ、動作フィードバックを受け取りやすい。結果、小さなエラーを早期修正できます。
4) ケガ予防と練習量の確保
足部の過回内・過回外、膝内側ストレス、前ももの過緊張などのリスクを抑えられるため、練習継続の総量を確保しやすい=上達が速い。
教学設計:3番 →(条件クリアで)→ 5番
当アカデミーでは、ポジションは教えるための“手段”。ゴールは踊りの再現性です。
-
3番での基礎確立
-
骨盤の中間位・肋骨の整列・頭頸バランス
-
股関節主導のターンアウト/膝つま先の一致
-
プリエ/タンデュ/デガジェの軌道・床とのやり取り
-
ルルヴェでの荷重コントロール(母趾球・小趾球・踵のバランス)
-
-
3番の強度アップ
-
片脚支持への移行、方向(エカルテ等)
-
動きの中で引き上げを保つ(重心移動時の骨盤管理)
-
-
5番の導入(進級基準を満たした方)
-
3番で得たアライメントと回旋を保ったまま交差を深める
-
5番でのプリエ・タンデュ・アッサンブレ等へ段階的に展開
-
よくある質問
Q. 5番は舞台で必要。最初からやるべきでは?
A. 必要です。だからこそ質の高い5番を目指します。3番で“ねじらない回旋”と“崩れない骨盤”を身につけてから移行すると、定着が圧倒的に速いです。
Q. 3番だと見映えが中途半端?
A. 3番は“半完成”ではなく、完成形(5番)への設計図。3番の完成度が上がるほど、5番のラインは自然に整います。
Q. 子どもは最初から5番の所も…
A. 年齢・可塑性・頻度が異なります。大人は安全で早い順序を選ぶのが合理的。同じゴールでも最短ルートは人によって違うという理解です。
3番「セルフチェック」(レッスン前後に)
-
立位で骨盤の中間位(反り過ぎ/丸まり過ぎになっていない)
-
肋骨を前に張らない、みぞおちが前へ落ちない
-
股関節からのターンアウトで、膝とつま先の向きが最後まで一致
-
プリエで膝が内側に倒れない、土踏まずのつぶれ/外側荷重の偏りがない
-
ルルヴェで足指の握り込み過多にならない、前ももに頼り過ぎない
-
アームスを載せても首・肩が固まらない(呼吸が楽)
5番導入(進級)の目安(当アカデミー例)
-
3番で連続ルルヴェ×8回:引き上げを保って安定
-
3番→オープン→3番のタンデュ往復:骨盤が流れない
-
3番プリエ:膝つま先一致が終始保てる
-
簡単なエシャッペの着地で体軸が崩れない
-
教師がアライメントの再現性良好と判断
まとめ
-
5番は到達点の一つ。
-
3番はその精度と速度を最大化するための“最短ルート”。
-
大人こそ、順序立てて学べば速く・きれいに・安全に上達できます。
体験レッスン/クラスのご案内
スケジュールやレベル説明は公式サイトからご確認ください。体験レッスンをご希望の方は歴に関係なく「入門クラスLv1」へをお勧めします。現在の状況に合わせて、最適な学びの順序をご提案します。