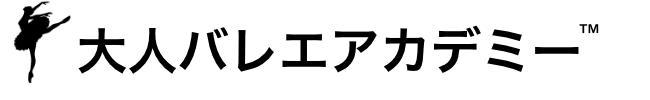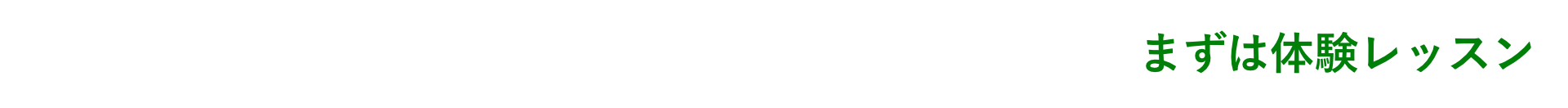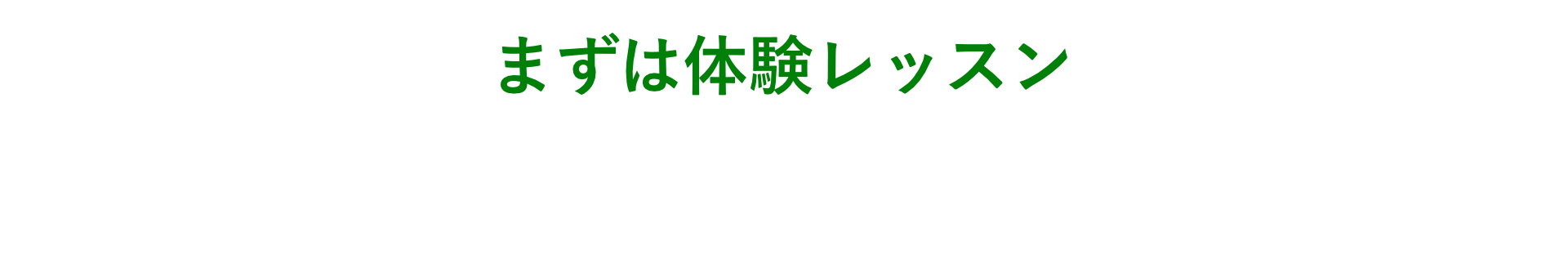— 箱(スタジオ)を広げる順番、間違っていませんか?
こんにちは。大人バレエアカデミー™、バレエトレーニングディレクターの猪野です。
まとめ
・団体の価値は「豪華な箱」よりも「そこにいる人」。
・団費に依存したまま固定費(家賃)を上げるのは、長期の競争力を削ります。
・年間スポンサーを得たいなら、まずはROIと透明性を整えるのが先です。
きっかけ:一等地160坪への移転とコスト感
最近、一等地に160坪の自前スタジオへ移転したという話を耳にしました。
仮に同ビル他フロアの坪単価が1.65万円なら、家賃は約264万円/月(=160×1.65)税抜。保証金・内装・仲介などを含めると、初期費用は数千万円規模(例:3,000万円前後)にもなり得ます。
ここで論点にしたいのは「移転の是非」ではなく、**“移転の順番”**です。
結論:先に“人と仕組み”、その後に“箱”
団体の価値はスタジオの豪華さではなく、優秀な人材が育ち集まる仕組みで決まります。
人材採用・育成・報酬設計 → 収益の再現性 → 必要に応じた移転という順番が、もっともリスクが低く、持続可能です。
団費がボトルネックになる理由
-
優秀層の参入障壁:プロ志向の人材は「価値を生み報酬を得る側」でいたい。団費は最初の時点で志望度を下げます。
-
課題の先送り:団費で固定費を埋める構造は、“収益力不足”という本丸を見えにくくします。
-
悪循環:人材が薄い→作品の質が下がる→収益が鈍る→さらに団費や寄付に依存、のスパイラル。
固定費アップの現実:売上目標は確実に上振れする
家賃264万円/月=年間約3,168万円。
箱の格は上がっても、その分毎月の売上目標が重くなるのは確実。人材の厚みや再演設計がない状態で本数だけ増やすと、品質低下と疲弊を招きます。
お金に無頓着で起こること(一般論)
「お金のことは考えたくない」「赤字ではない“らしい”」という姿勢は、内部統制の弱さにつながります。もし不正があれば損金にできず追徴課税という事態も(※特定の団体を指すものではありません)。高固定費の環境ほどダメージが大きいのも現実です。
年間スポンサー募集への違和感(企業目線)
単発の商品告知目的ならスポンサー出稿はありえます。
ただし、お金にシビアな経営者やCFOが年間スポンサーとして意思決定するには、次が必要です。
-
費用対効果の設計:到達・想起・来場・購買など、計画が明確か。
-
透明性:使途の可視化、レポーティング、第三者レビューが機能しているか。
-
ブランドセーフティ:ガバナンスが効き、不祥事・内部不正のリスクが低いか。
団費依存+高固定費+財務の不透明さが見えると、年間契約は“ほぼ審査落ちです。
現実的には、公演単位や企画単位のスポンサーで成果とレポートを積み、勝てる型を証明してから年間化を打診する流れが、健全で通りやすいです。
まず整えるべき“8つの土台”
-
団費ゼロ化のコミット(期限と段階計画を公開)
-
評価×報酬の透明化(役割・成果・再現性で報いる)
-
反復収益の柱(教育事業、再演設計、デジタル配信、コミュニティ)
-
KPI設計(客単価、稼働率、再演率、LTV 等)
-
案件ごとの簡易P/L開示(毎回でOK)
-
内部統制の基本(職務分掌、二重承認、支出ログ、外部レビュー)
-
危機管理手順(中止・返金・情報開示の判断プロトコル)
-
スポンサー価値の明文化(露出・体験・接点・データ/レポート)
この8点が揃って初めて、**年間スポンサーという“長期の信任”**が現実味を帯びます。
ロードマップ(順番を間違えない)
-
Step1:団費の段階的撤廃(減額→ゼロ。期限を切る)
-
Step2:人への投資(採用・育成・評価と報酬の設計)
-
Step3:反復収益の確立(教育・再演・デジタルを軸に)
-
Step4:可視化(KPIと簡易P/Lの定点開示)
-
Step5:内部統制の最低ライン(仕組みで組織を守る)
-
Step6:必要になってから移転(人材・再現収益・統制が揃ってから)
おわりに
バレエ団が本当にやりたいのは、良い作品を継続的に世に出すこと。
それを支えるのは箱ではなく、ひとと仕組みです。
だからこそ、団費より「人」へ投資し、透明性と再現性を整える。
この順番を守る団体が増えたとき、バレエ界の未来はもっと強く、しなやかになります。