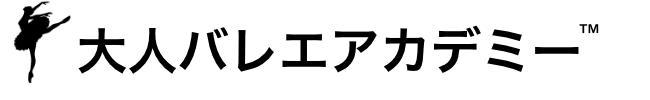こんにちは、東京、横浜、大阪梅田で運営する大人バレエアカデミー™
バレエトレーニングディレクターの猪野です。
バレエのレッスンでよく聞くアドバイス、「もっと筋肉を使って!」。
でも、これってまるでRPGで突然「そこの石板を使え!」って言われるのと同じくらい、
具体的に何をすればいいのか迷いませんか?
バレエに必要なのは美しい「形」。その形を作ろうとすれば、体は勝手に筋肉を使うはず。
なのに、なぜわざわざ「使え」と言われるのでしょう?
筋肉の特性を考えると、縮むことしかできないのに、「伸ばすように」見えたりして、
本当に よくわからない!
なぜ「もっと筋肉を使って」と言われるのか?
確かに、ポーズを取ったり、足を上げたりする時、筋肉は自動的に働いています。
しかし、「もっと筋肉を使って!」という指示には、自動的な反応以上の深い意味が込められています。それは、
- 意識的なコントロール: どの筋肉を、どれくらいの強さで、どんなタイミングで使うのかを意識的にコントロールすること。無意識の反応に頼るのではなく、自分の意思で筋肉を操ることで、より正確で洗練された動きが可能になります。
- 質の向上: ただ形を作るだけでなく、その質を高めるため。例えば、同じアロンジェでも、ただ腕を伸ばすだけでなく、背中や肩甲骨周りの筋肉を意識的に使うことで、より伸びやかで優雅な表現が生まれます。
- 安定性と軸の強化: 体の中心にある深層筋を意識的に使うことで、体の軸が安定し、バランス感覚が向上します。ぐらつきのない、しっかりとした踊りの土台を作るために不可欠です。
- 怪我の予防: 正しい筋肉の使い方を身につけることで、関節への負担を減らし、怪我のリスクを軽減します。間違った使い方で無理に動かすのではなく、適切な筋肉を活性化させることで、安全にトレーニングできます。
筋肉の基本的な性質は「収縮」です。しかし、バレエの動きの中で「伸ばすように見える」現象は、
以下の筋肉の巧妙な働きによって生まれます。
- 拮抗筋のコントロール: 関節を曲げる筋肉(主動筋)が収縮する時、反対側の筋肉(拮抗筋)がただ緩むだけでなく、わずかに制御された収縮をすることで、動きが急激になるのを防ぎ、滑らかで伸びやかな印象を与えます。例えるなら、ブレーキをかけながらアクセルを踏むようなイメージです。
- 遠心性収縮(エキセントリック収縮)の活用: 筋肉が収縮しながらも、その長さを伸ばされる方向に抵抗する働きです。例えば、アロンジェで腕をゆっくりと伸ばす際、肩や背中の筋肉は収縮していますが、同時に腕の重みで引き伸ばされています。この制御された抵抗が、美しく、コントロールされた「伸び」を生み出します。
- 関節の可動域と筋肉の連動: 関節が持つ最大限の可動域を引き出すためには、複数の筋肉が協調して働く必要があります。ある筋肉が収縮して関節を動かすと同時に、別の筋肉がその動きをサポートしたり、安定させたりすることで、全身を使ったダイナミックな「伸び」が表現されます。
「もっと筋肉を使って!」という指導が抽象的に感じられるのは、RPGで「石板を使え!」と言われるのと同じで、具体的なアクションが不明確だからです。
もしRPGで「石板を使え!」と言われたら、
もしRPGで「石板を使え!」と言われたら、
- 「どこで?」
- 「どうやって?」
- 「何のために?」
と疑問に思いますよね。
バレエの「もっと筋肉を使って!」も同様です。
バレエの「もっと筋肉を使って!」も同様です。
- 「どの筋肉を?」
- 「どのように活性化させるの?」
- 「その結果、どんな動きにつながるの?」
これらの疑問が解消されないままでは、ただ漠然と力を入れてしまい、かえって動きを硬くしたり、間違った筋肉を使ってしまう可能性があります。
だからこそ、バレエを学ぶ上で非常に重要なのは、筋肉の使い方を定義のはっきりした言葉で説明してくれる指導者に出会うことです。
もしあなたが「もっと筋肉を使って!」という指示にいつも戸惑ってしまうなら、
先生に積極的に質問してみることをお勧めします。
「具体的にどの筋肉を意識すればいいですか?」
「この動きでその筋肉を使うと、どう変わりますか?」
と質問することで、より深い理解につながるはずです。
そして、もし可能であれば、体の使い方や解剖学の知識をしっかりと持っている指導者のもとで学ぶことを強くお勧めします。
具体的な言語化ができる指導は、あなたのバレエを確実にレベルアップさせてくれるでしょう。
バレエにおける「筋肉を使う」とは、単に力を入れることではありません。
それは、意識的なコントロール、拮抗筋との協調、深層筋の活性化、
そして遠心性収縮などの高度なテクニックを含む、複雑な身体操作の指示です。
「もっと筋肉を使って!」という抽象的な指示に迷ったら、
具体的なアクションを理解することが大切です。
そのためには、筋肉の使い方を明確に言語化してくれる指導者を見つけることが、
上達への近道となるでしょう。